➤逆境のエンジェルとは
アメリカで暮らす筆者が、いじめ、身体障がい、音楽への情熱、異文化での生活、人種差別、仏教との出会いを通じて成長していく物語。個人的な体験を超え、社会の不平等や共生の課題にも鋭く斬り込み、逆境のなかで希望を見出す力を描きます。
➤前回のあらすじ
トラウマについてもう少し深掘りして、実際にアメリカではどのような試みがされているのか。また、筆者の臨床経験も含めて語っています。(第57話『声にならない声を聴く』)はこちらからご覧ください。
屋台の香に誘われて
バター醤油をたっぷり塗った焼きとうもろこしの香ばしい匂いが漂う午後。どこか懐かしいお囃子(はやし)が風に乗り、ステージ脇では和太鼓が本番前の静かな緊張を帯びて並んでいる…。
ここは北カリフォルニア・ベイエリア。毎年9月の最終日曜日、シカモア組合教会で開催される恒例の秋祭りが、今年も快晴に恵まれたなかで幕を開けました。
少し汗ばむ陽気のなか、日本の秋祭りを思わせるような空間に、人々の笑顔がまばゆいばかり。私は和太鼓の演奏グループの一員として参加し、リハーサルの合間にカメラを手に祭りの風景を眺めていました。
目に飛び込んでくるのは、カレーライス、うどん、お寿司、ステーキ弁当といった日本食の屋台。どれも魅力的で、何を選ぼうかとつい目移りしてしまいます。

祭りの会場では、テーブルやベンチが来場者で埋まり、日本語と英語が交錯する声が絶え間なく響いています。日本人も日系アメリカ人も、世代や背景を越えて笑顔で語り合う光景は、どこか懐かしく、そして温かいのです。
カメラを向けると、「ここも撮って!」「お寿司買ったよ!」と笑顔で応えてくれる。私はその瞬間、不意に「アイデンティティ」という言葉が頭に思い浮かびました。

「日本語は禁止だった」〜言葉に刻まれた痛み〜
私が所属している和太鼓クラスのメンバーは、私以外全員が日系アメリカ人です。30代から70代まで、年齢層は広く、それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながら、太鼓のリズムを通じてつながっています。
ある日、リハーサルの合間に何気なく「日本語、話せますか?」と尋ねたことから、思いがけない会話が始まりました。
「私の両親は日本語を話すことを絶対に許してくれませんでした」
その場にいた他のメンバーも、うなずきました。「うちもそうだった」「家では英語だけだった」と。それは偶然ではなく、戦後アメリカに生きた日系人たちにとっての当たり前の姿だったのです。
特に、第二次世界大戦中の強制収容や差別の歴史を経験した親世代は、子どもたちに“日本人であること”の前にアメリカ人であることを求めたのです。
日本語は、文化の象徴であると同時に、『疎まれる印』でもありました。だからこそ、家庭内で日本語を話すことを禁じ、必死でこの国の文化に馴染み溶け込もうとした軌跡が伺えます。
私たちは見た目こそ同じ「日本人」ですが、言葉、文化、家族の記憶のなかに流れているものはまったく異なるのです。
私にとっての日本語は、母国語であり、思考や感情のベースですが、彼らにとっては、歴史の記憶と、どこか遠い存在でもあるのです。

ジャズが呼び起こす記憶
そんな会話の記憶が鮮明に残るなか、数日後、ジャズグループ「OTONOWA(音の輪)」の演奏会に足を運びました。
OTONOWAは、日系アメリカ人によるジャズグループです。メンバーの多くは、アメリカで活躍するトップクラスのジャズミュージシャン。
彼らの演奏には、日本の伝統的なメロディがふんだんに取り入れられています。『待ちぼうけ』『赤とんぼ』『どんぐりころころ』など、日本人の心に深く根差した旋律が、ジャズという異なる音楽形式の中で再構築され、息を吹き返していくのです。
このグループは東日本大震災の後、毎年現地に赴き演奏を通して、被災者の方々を勇気づける活動を行っています。
このグループのリーダーのタナ・アキラさんによると、震災のときまでは、それほど多くの日本のフォークソングは知らなかったといいます。「待ちぼうけも、どんぐりころころも、知らなかったんだ」と語ってくれました。
演奏が始まった瞬間、私は思わず一緒にサックスの奏でる『どんぐりころころ』や『待ちぼうけ』を口ずさみ、懐かしい気持ちに包まれました。

以前、誰かがいっていた、「音楽には国境がない。でも、音が呼び起こす記憶には、その人のふるさとや、家族や、文化がある」
その言葉が、太鼓クラスの日系アメリカ人の、「日本語を話せなかった」という言葉と重なりました。文化を語ることは、ときに古い傷に触れることになりますが、音楽は、そんな記憶をそっと包み込み、癒してくれる力を持っています。
アイデンティティは「問い」であり「現在地」
アメリカという多様性に満ちた社会に生きていると、「自分は何者か?」という問いに直面することが多々あります。言語、文化、名前、肌の色…。さまざまな要素がアイデンティティを構成する一方で、社会の目や歴史によって、それが複雑な形になっていることも多いのです。
私にとって和太鼓を叩くことは、日本の文化を体現することです。しかし、同時に自分自身を見つめ直す時間でもあります。
今回、仲間たちの「語れなかった記憶」に触れて、ただ日本文化を披露するというだけではない『重み』を感じました。
毎年開催される秋祭り。多くの人が集まるこのお祭りには、「繋がりたい」という願いが込められているように思いました。

そして、OTONOWAの演奏が教えてくれたのは、文化は過去を懐かしむだけのものではなく、“いま”を生きる力にもなり得るということ。
アイデンティティとは、自分の出どころを確認するだけのものではなく、それは、「いま、どこにいて、どんな思いで生きているか」という確認でもあるのかもしれません。
次回は、30年以上続いた古本市のお話。いよいよ閉店になるこの店で、そこに関わる方々と、小さいけれど確実に息づく日本人コミュニティーについて語っていきたいと思います。
第59話はこちら
記事の一覧はこちら
(感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、作者エンジェル恵津子さんのエネルギーとなります。よろしくお願いします。by寺町新聞編集室)


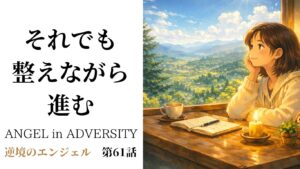

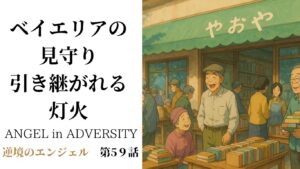
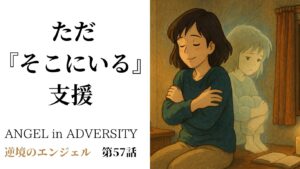
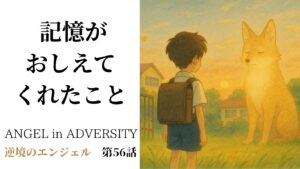
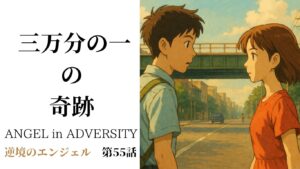
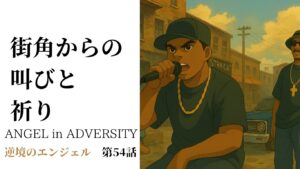
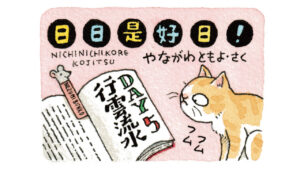
コメント