➤逆境のエンジェルとは
アメリカで暮らす筆者が、いじめ、身体障がい、音楽への情熱、異文化での生活、人種差別、仏教との出会いを通じて成長していく物語。個人的な体験を超え、社会の不平等や共生の課題にも鋭く斬り込み、逆境のなかで希望を見出す力を描きます。
➤前回のあらすじ
編集室に届いたある読者のお便りから、人生について語っています。(第55話『交差する人生と、支え合う事実』)はこちらからご覧ください。
“Suicide Prevention Awareness Month”〜記憶が教えてくれたこと
9月のアメリカは “Suicide Prevention Awareness Month(スーサイダル・プリベンション・アウェアネス・マンス)”。スーサイダル・プリベンションとは自殺予防のこと。つまり、自殺予防を考える月間です。
日本でも9月1日の前後には、いわゆる「9月1日問題」が語られます。夏休みが終わり、新学期という節目に胸が締めつけられる子どもたちがいる。その現実はアメリカも同じです。
私自身、この時期の苦しさを知っています。学生時代、夏休みが終わる1週間ほど前になると、宿題のプレッシャーだけでなく、またいじめられるかもしれない、また教室に溶け込めないかもしれない…という不安に飲み込まれる夜がありました。
胸の奥に鉛を抱えたまま朝を迎え、食事もあまり喉を通らず、頭のなかでは「お腹が痛いといって休もうか」という考えまで浮かぶ。
あの感じを、いまでもはっきり覚えています。だから、9月1日に向かう独特の「苦しさ」は、私にもよくわかるのです。
こうして自分の記憶を並べてみると、胸のざわめきや体のこわばりは「ただの気分」ではなく、心と体が学び取った反応だとわかります。言葉にするなら、それは「トラウマ」の働きと重なっています。

トラウマとは何か
近年、心の健康について語られることが増えました。その中核にある言葉がトラウマです。
トラウマとは、心や体が受けた強い衝撃によって刻まれる深い傷。出来事そのものだけでなく、匂い・音・場所と結びついて、ふいに現在を曇らせることがあります。
理屈では「もう終わった」とわかっていても、体は過去の時間を生き続けてしまう。そのズレに、私たちは苦しくなります。
小さな棘(とげ)のこと【香りの記憶】
私にもいくつかの小さなトラウマがあります。
ひとつは、熟れたバナナの香りが苦手というもの。幼いころ、全身麻酔のマスクから漂った果物めいた薬品の香りが体に深く染みつき、「イチゴがいい」と伝えた私に医師が、「ごめんね、バナナしかないんだ」と告げた、その声と匂いだけが、薄れる意識のなかで強く残りました。
いまも甘い香りがふっと漂うと、過去への扉が開くのを感じます。
日常を狭くする引き金【物置の扉】
もうひとつは、職場の物置部屋です。
最初の異変を感じてから発見まで半年以上かかったネズミの死骸。さらに4年前、整理中に棚から飛び降りて足元をかすめたネズミ。
外から見れば取るに足らない出来事かもしれません。
けれど、ドアノブに指をかけるたび、理性は「大丈夫」とささやくのに、体は震え、息が浅くなります。
トラウマは、ときに日常の小さなことをきっかけに、生活の一部を静かに困難にしていきます(それくらいのことと見える出来事でも、当人にとっては感覚が先に反応するのです)。
カレンダーが連れてくる不安【冬から夏へ】
時期的なものもあります。私は小学生の頃、新年が明けるとすぐに不安が心を支配しました。半年も先のことなのに、水泳の授業の思い出が私を悩ませるのです。
当時、泳げなかった私を、教師は容赦なくプールに何度も投げ入れました。鼻から入る水の痛み、パニックになって水を大量に飲んだこと、同級生に水着姿を笑われた記憶…。その束が、季節をまたいで私を縛りました。
こうして並べてみると、出来事は過去にあるのに、反応はいまここで起き続けることがわかります。では、この反応にはどんな種類があり、どこから来るのでしょうか。

トラウマのいくつかの顔
トラウマにはいくつもの種類があります。
- 急性トラウマ:事故・災害・暴力など、一度の強烈な出来事で生じる。
- 慢性トラウマ:いじめやDV、継続的な侮蔑(ぶべつ)や排除など、長期にわたる体験の積み重ね。
- 複雑性トラウマ:幼少期など発達の要所で繰り返し安全が壊れる体験。
- 世代間トラウマ:直接経験していない傷が、家族や共同体の歴史を通して感情や反応に影を落とすもの。
このうち耳慣れない言葉が「世代間トラウマ」かもしれません。これは、直接受けた傷ではないけれど、深く心に根をはる、深刻なトラウマだといえます。
世代間トラウマの具体例
人種差別の歴史は、その一例です。
長い年月にわたる差別や排除、監視するまなざし、住む場所や教育・就労機会の制限…。その積み重ねは、つねに周囲を警戒するクセ(過覚醒)や、失敗を極端に恐れる感覚、安心できる場所でも「自分は歓迎されていないかもしれない」という前提につながることがあります。
本人が差別を受けた記憶を語らなくても、祖父母や親が沈黙して背負った歴史が、家族の空気や日常の選択ににじみ、無言のルールとして伝わってしまうのです。
家庭環境にも例があります。
戦争体験や極度の貧困、家族内の暴力、依存症などで、親の世代に「安全はいつも突然失われる」という学習が刻まれていると、次の世代は大声や足音、物音への過敏さ、衝突を避けて本音をいえないクセ、あるいは逆に感情が爆発してしまう反応として現れることがあります。
どれも、生き延びるために身につけた、不器用な知恵の形だといえます。
体は生きようとしている
ここで、大愚和尚の言葉を思い出します。
「心が死を選びかけていても、体は生きようとしている。傷ついた体は、その瞬間から修復を始める」。
この一節を初めて聞いたとき、私は衝撃を受けました。
そうか――。もしいま、心が暗い水の底に引きずられているように感じても、体のどこかでは、確かに生の側に向かう働きが続いている。その事実自体が、小さな希望の光になるのだと。
仏教の視点:苦と手放し
仏教では、人の生には「苦」がつきまとうと率直に語ります。これだけを聞くと暗く思えるかもしれませんが、ここで示されているのは絶望ではなく、現実への眼差しです。
9月1日に向かう胸の重さ、教室へ向かう足のすくみ、匂いひとつで過去にさらわれる瞬間 …。
それらを「あってはならない」と押しやらず、「確かに、ここにある」と見つめて受け入れる。苦を否定しないとき、私たちは初めて自責や固執から少し離れ、前に進む選択肢が見えてくるのではないでしょうか。
そして「手放す」。ここでいう手放しは、無理に忘れることでも、気合いで克服することでもない。握りしめているものに気づき、指を一本ずつ、ほどくように力をゆるめることです。
握りしめていたのは恐怖だけではありません。「強くあらねばならない」「早く治さねばならない」「迷惑をかけてはならない」。
そんな掟を手のなかで固く握りしめ、血が通わなくなっていたのかもしれない。少しずつほどくと感覚が戻り、体が呼吸を思い出す。ゆるみが生まれると、選択の幅が広がります。

日々の手がかり
行ける場所・話せる相手
辛いときに行ける場所、話せる相手がいる。そのシンプルな事実が、確かに心の救いにつながるのだと思います。
私が週末にパート勤務をしているメンタルクリニックでも、子どもや10代の若者が、同じ境遇の同世代の顔を見るだけで、肩の力が少し抜けたり、短い会話のなかで「自分だけじゃない」と確かめられたり。環境が変わることで、気分がすっと上向く場面を何度も見てきました。
大切なのは、こうした支えが医療機関でなくても成立するという点です。
身近なお寺や神社で、住職さんや神職の方にひとこと声をかける。公民館のラウンジや、地域の食堂の一角が静かに開かれていて、ただ座ってもいい、少し話してもいい、泣いてもいい。
そんな場が日常にあるだけで、心はずいぶん楽になります。地域のなかに、気軽に立ち寄れて、深刻な話も他愛ない話もできる場所が増えてほしい ーーそう強く感じています。
次回は、今回のテーマをもう少し深掘りして、実際にアメリカではどのような試みがされているのか。また、筆者の臨床経験も含めてお話しいたします。
第57話はこちら
記事の一覧はこちら
(感想、メッセージは下のコメント欄から。みなさまからの書き込みが、作者エンジェル恵津子さんのエネルギーとなります。よろしくお願いします。by寺町新聞編集室)

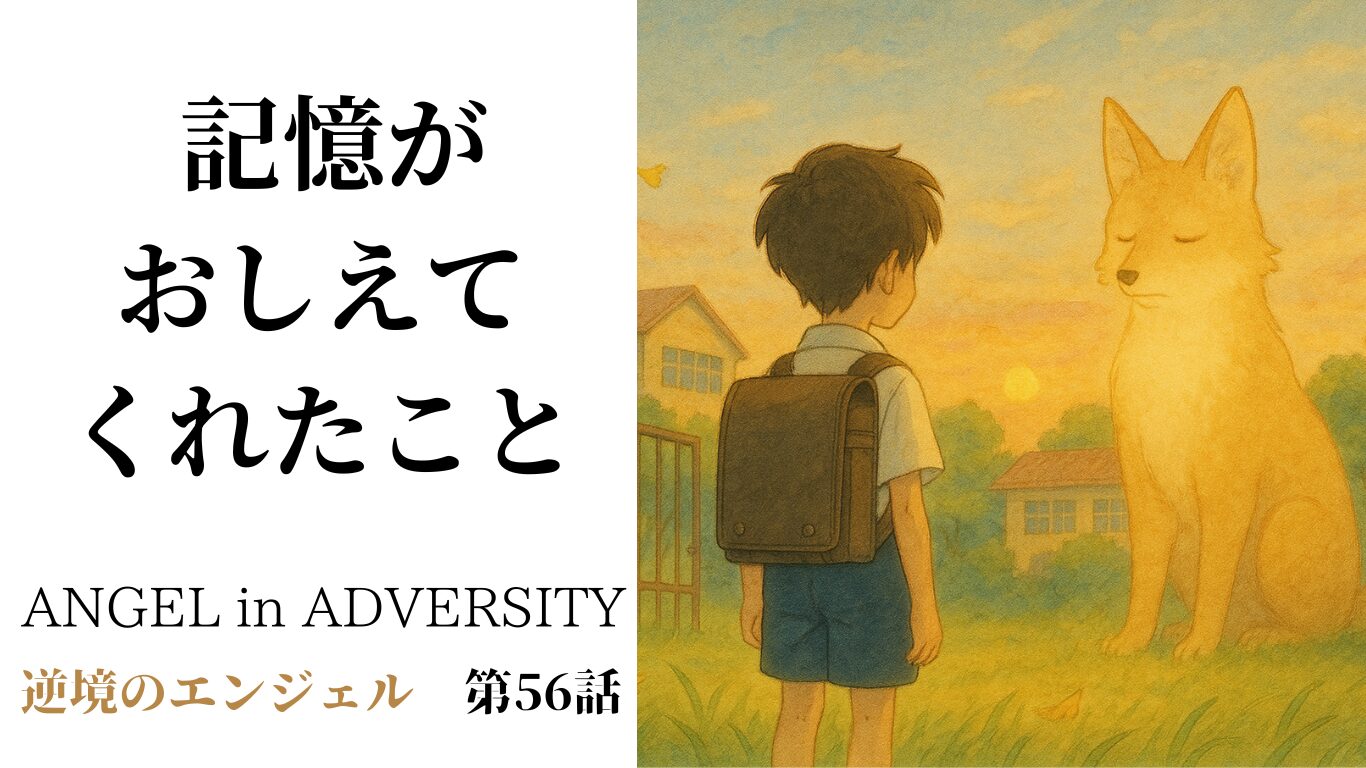
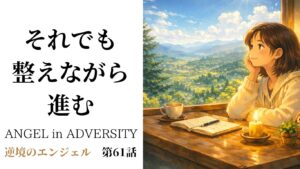

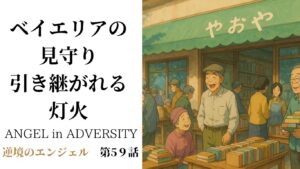
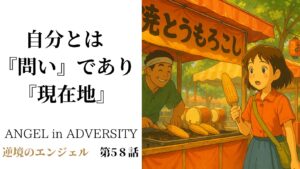
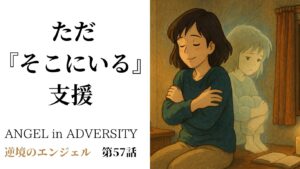
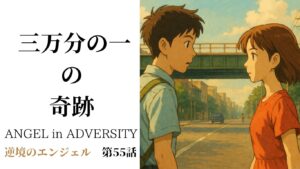
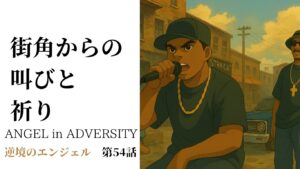
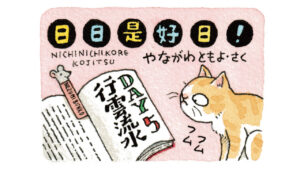
コメント