物静かで恥ずかしがり屋だった少女が、高校の交換留学をきっかけに海外へと歩み出し、ニュージーランドやアメリカで成長していく姿を描いた第1弾。特に「母は目標の人」という言葉が印象的でした。そこには、亡きお母さまとの深い絆が語られていました。
第2弾では、お母さまの葬儀を経て再び始まったアメリカでの生活、そして仏教との出会いを通して、裕月さんがどのように“いま”を築いてきたのか、その答えを探っていきます。
「自分は取り残されている!」出産後に訪れた閉塞感
◾️お母さまを見送られ、アメリカに戻られてからの生活はいかがでしたか?
裕月:アメリカに戻り、すぐに仕事に復帰しました。その後、貿易関係の仕事に就いたのですが、ビザの関係でまた日本に帰らねばならなくなりました。2008年、主人とは婚約状態で大阪に行き、2009年に入籍。翌年3月に長男を産みました。
ビザが取れるまでの数年間、大阪で暮らし、その間にふたり目の子どもを出産。2012年にアメリカに戻るまで、家族4人で楽しく暮らしていました。
しかし、アメリカに戻ってからは、閉塞感を抱くようになりました。私のなかには「社会で認められる自分になりたい」という思いがあったので、育児と家事が中心の生活には、正直、焦りを感じましたね。家のなかに閉じこもっていることが、とても辛かったです。
◾️親族や知人に支援を求めることはなかったのですか?
裕月:はい、誰かの助けを借りることはなく、自分たちだけで育児をしていました。
しかし、なんでも自分たちで抱え込んでしまったことで、「社会から取り残されている」という不安はどんどん大きくなってしまい、自信がなくなってしまいました。いま振り返ると、とても幸せな時間だったのに…。それを純粋に楽しむことができなかったことに、少し後悔もありますね。
大愚和尚との出会いに救われて
◾️そんななか、仏教と出会われたのでしょうか?
裕月:はい、いまから4〜5年前のことです。当時は3番目の子どもも生まれていたので、外で働くことが困難でした。閉塞感がピークの、私にとって一番大変だった時期でしたね。
そんなモヤモヤした気持ちを晴らすために、YouTubeで自己啓発の動画をたくさん見ていました。そんなとき、大愚和尚さまの動画が目に留まり、それが人生の転機となりました。
◾️どのような内容が心に響きましたか?
裕月:「自分でさえ自分のものではないのに、みんなお金や子どものことで悩む」という話でした。それを聞いて「自分って自分のものじゃないんだ、ましてや子供やお金は自分でコントロールできるものではないんだ。」と気づかされました。
そして、それまで悩んでいたことが、少し楽になりました。
◾️それが大きな転機になったのですね。
裕月:そうです。その後、和尚さまの『苦しみの手放し方』という本を読みたくて、夫に頼んでキンドル(電子書籍)を購入しました。そこには本当にたくさんの学びがありました。
その後、無料メルマガにも登録し、メールを通じてさらに多くの学びを得るようになりました。
やがて『一問一答』を外国語に訳す「翻訳クラブ」の存在を知り、志願しました。自宅にいながら社会に貢献できる道を見つけたことで、とても救われた気持ちになりましたね。「翻訳クラブ」での活動を通じ、現在も多くの人とつながる機会をいただいています。
◾️昨年のロサンゼルスでの大愚道場では、司会を担当されていましたね。
裕月:はい。自信があったわけではないのですが、「いただいた役割は断らない」という考えで挑戦しました。その結果、自分の可能性を広げるいい経験になったと感じています。


ようやく見つけた、自分に合った仕事
◾️その後のお仕事について教えてください。
裕月:3年ほど前、航空機や自動車関係の日系の貿易会社に入り経理の仕事に就きました。
心理学の学位はあまり活かすことができず、親には申し訳ないのですが、細かい作業が好きなので、こういう仕事が自分に合っているなと感じました。
◾️ご自分に合ったお仕事に出会えたのですね。現在もそのお仕事を?
裕月:いえ、2年半ほど経理士の仕事をした後、ステップアップしたいと思い、つい最近、転職をしました。手術の際、体に入れるカテーテルの製造販売を行う会社で、セールスサポートとして働いています。
◾️そうなんですね、転職おめでとうございます!
裕月:ありがとうございます。新しいことを学ぶのは大変ですが、やりがいを感じています。
仏教の教えを仕事に活かして
◾️お仕事をするなかで、仏教の教えが役立っていると感じることはありますか?
裕月:はい、仏教の教えが基本にあるおかげで、毎日を前向きに過ごせています。
やはり、仕事って人間関係ですよね。和尚さまがよくおっしゃておられる「日常五心(※)」。職場の人間関係を良好に保つために、この姿勢を忘れないようにしています。
小さなことの積み重ねではありますが、以前の会社でよくしていただけたのも、この日常五心を心がけていたからだと思います。
◾️仏教の教えが裕月さんの人生に深く関わっているんですね。
裕月:はい。そのおかげで、自分自身の考え方や、人との接し方が大きく変わりました。
※日常五心:「はい」という素直な心、「すみません」という反省の心、「どうぞ」という謙譲の心、「私がやります」という奉仕の心、 「ありがとう」という感謝の心 という5つで構成された大切な心もちのこと

授戒を受けて定まった、進むべき道
◾️裕月さんは昨年5月、ロサンゼルで授戒会を受けられたと伺いました。
裕月:はい。戒名には母の名前を、和尚さまが入れてくださいました。実はその文字「孝」は、母はあまり好きではなかったんです(笑)。「たかし」とも読めるので、男の子みたいで嫌がっていたんですよ。
でも、私にとってはこれが母の名前なんです。
道号(※)は「孝薫(こうくん)」というのですが、私はこの名前をいただいたことで、母の徳をちゃんと受け継ぐことができると感じています。母がどう思っているかわかりませんが(笑)。
◾️きっと喜んでいらっしゃいますよ。
裕月:だといいですね。この名前のおかげで、母にずっと守られている気がします。
◾️戒名は、和尚さまが裕月さんのお書きになった文章をじっくりお読みになって、考えてくださったのですね。
裕月:はい、その名前を目にしたときは、うれしさで涙が止められなくなりました。すてきなお名前をいただいたと思っています。

◾️戒名をいただいて、これからどのように生きていこうと思われますか。
裕月:仏教でいうところの「慈悲心」を持つことですね。
慈悲心を正しく持つのは本当に難しいと思います。この人にとって、本当にいいことは何だろうと思っての慈悲心でなければいけませんから。
一見いい人に見える行為をすることは、とても簡単なこと。でも、本当の慈悲心とは、ときには少し心を鬼にして、距離を置かないといけないこともありますよね。
◾️ときには厳しいことを言わなければならない、ということですね?
裕月:そうですね。戒名の字を思い浮かべるとそこに立ち返ることができるので、目標がはっきりわかって生きやすくなった気がします。
◾️目標ができることで進むべき道が定まる、というわけですね。
裕月:そうですね。そうした目標も、若い頃から持っていると、迷うことがなくなりますね。和尚さまは名前に道を示してくださっているので、きっとこれからの人生が生きやすくなると思います。授戒会を考えている方には、ぜひおすすめしたいですね。
◾️仏教に出会われたタイミングについてはどのようにお考えですか?
裕月:もう少し早かったら、という気持ちもありますが、私にとっては、あのときが絶妙のタイミングだったと思っています。
人間の転換期というのは、緩やかにくる人もいれば、突然やってくる人もいる。
タイミングは人それぞれにあって、早く決断しても遅く決断しても、その人に見合ったタイミングであれば、それがベストなのだとも思います。
※ 道号(どうごう):戒名の上につく、戒名を構成する要素のひとつ。本人の人柄や性格、仕事、趣味などがわかる称号

「普通」のありがたみに感謝する
◾️アメリカで生活する上での難しさや、老後に対する思いなどがあれば聞かせてください。
裕月:アメリカは好きですが、老後は日本でと考えています。住みやすく快適ですし、福祉も充実、医療保険の面でも安心ですね。
アメリカの老人ホームはとても高いので、私の場合、入所はまず無理だと感じています。
アメリカの医療保険制度も、複雑で高額です。元気なときならまだしも、高齢になって薬もいろいろと必要になったとき、経済的に大変になると思っています。
外国に暮らしている方は、みなさん何かしらそういう不安をお持ちではないでしょうか。
◾️逆に暮らしやすいのはどんなところですか?
裕月:ひとことでいうと自由な空気とでもいいましょうか。しきたりもそれほどきつくなく、いろいろな人がいるからか、他人の目は寛容で過ごしやすいと感じます。


◾️最後に、これを読まれているみなさんにメッセージをお願いします。
裕月:日本は本当に素晴らしい国です。一度海外に出てみると、日本のよさがよりわかると思います。
人を気遣ったり、礼儀も正しいなど、人間性が豊かだと感じますし、物もとても丁寧につくられていますよね。質もいいですし。
たとえば家の水回りに関しても、アメリカでは、日本では考えられないことがよく起こります。
構造的に問題があるのか、水回りがよく詰まるし、それが当然のようになっています。業者さんを呼んで直してもらうのですが、いくら修理してもすぐにダメになってしまいます。
◾️確かに、日本ではそういうことはあまり聞かない気がします。
裕月:アメリカにいると、そういうトラブルへの対処が大変ですが、そのぶん忍耐力がついて、やがて動揺しなくなるんです。ちょっとしたことでは動じなくなりますね。
電車が5〜10分来なくても、「そのうち来るだろう」と思えるようになりますから。
日本の人は、日本の当然が海外では当然でないことを知るためにも、1回外に出てみることをおすすめします。
そうするともっと強くなれるし、「日本での普通」のありがたみを感謝できるようになるでしょう。「なんて快適なんだろう、この快適さは当たり前じゃないんだ」と実感できます。
◾️確かに、そういう経験も必要かもしれませんね。本日は、ありがとうございました。
裕月:こちらこそ、ありがとうございました。
オレンジカウンティについて
オレンジカウンティはカリフォルニア州南部、ロサンゼルス郡とサンディエゴ郡の間に位置する郡で、海辺の落ち着いた雰囲気から富裕層に人気があります。人口は州内でロサンゼルス郡、サンディエゴ郡に次いで多いです。
オレンジカウンティのなかにあるアナハイム市は、ロサンゼルスの南東40kmに位置する、ディズニーランドで有名な街です。1857年にドイツ人移民が入植し、サンタ・アナ川の「Ana」と、ドイツ語で家庭を意味する「Heim」を組み合わせて名付けられました。
もともとはアメリカ原住民のトンバ族が住んでいた地域ですが、スペイン統治時代に牧場や伝道所が設立され、のちにアメリカの一部になると土地開拓が進みました。
1857年には、ドイツ系移民がアナハイムをワイン製造拠点として開発。20世紀初頭には日本人移民が住み始め、農業に従事し、オレンジやイチゴの栽培で成功しました。しかし、1941年の真珠湾攻撃後、多くの日系アメリカ人が強制収容所に送られ、財産を失う苦難を経験しました。
戦後は日系人がこの地域にコミュニティを再建。現在、日系アメリカ人コミュニティが主催するイベントや施設(例:アナハイム日本文化センター)などを通じて、日本文化が地域社会に深く根付いています。

取材を終えて
交換留学をきっかけに芽生えた海外への憧れ、ニュージーランドやアメリカでの生活を通じて育んだ自立。さらに、大学時代の母親の病や死を通して生じた葛藤と、結婚や育児における苦悩…。そうした日々を経て出会った仏教から、救いや学びを得た裕月さん。
この出会いが人生観を形づくる大きな転機となり、お母さまの名前にちなんだ戒名を、生きていく上での指針に据えておられる。その真摯な姿には胸を打たれました。
アメリカ生活で体験された数々の試練を確実に強さに変えている、その頼もしい様子から、生き方を見つめ直すヒントをいただくことができました。
このシリーズでは今後も、さまざまな国で奮闘する日本人、日本で挑戦する外国人。などなど様々な人生の物語をお届けしていきます。どうぞご期待ください。
裕月さんオススメ動画「大愚和尚の一問一答」
(取材:エンジェル恵津子)
(感想、メッセージは下のコメント欄から、よろしくお願いいたします。by寺町新聞編集室)



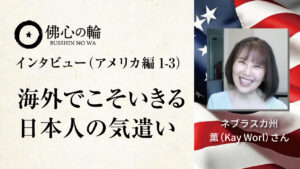
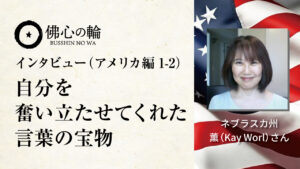
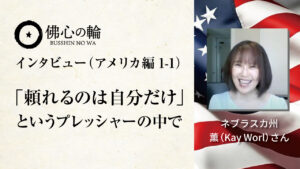


コメント