秋の深まりが感じられる2022年10月29日、福厳寺にて授戒会が執り行われました。前回の記事では、戒名の成り立ちと、参加者3名のインタビューを紹介。授戒した背景や未来への想いをお伝えしました。
最終回の本記事では、過去に授戒した方々が現在どのように暮らしているかのインタビューと、授戒会での大愚和尚の法話をご紹介します。ぜひご一読ください。
「教えの種」をまく | 智潤工導(ちじゅんこうどう)さん
まずは2020年に授戒された智潤工導(ちじゅんこうどう)さんです。現在はロボット工学の研究者として活躍。人が豊かに暮らすための、人の生活を支援するロボットシステムの研究開発に取り組んでいます。
授戒した直後は「戒名を授かったことを自然に受け入れていた」といいます。しかし、日を追うごとに戒名を授かったことへの自覚が生まれ、戒名の意味と、自らの行動を照らし合わせながら暮らすようになっていきました。

学校では、自身の研究だけでなく、学生を教えるのも仕事。教える側として、学生を「どこでも活躍できる人」に育て導くことが求められ、そのためには忍耐が必要になります。問題を抱えやすい、目標が達成できず悩んでいる、といった学生を決して見捨てることなく、根気強く最後まで寄り添わなければなりません。
しかし、どうしようもなく怒りや焦りの気持ちが湧いてくることも。そんな気持ちにどう向き合うかを悩んでいたところ、YouTube「大愚和尚の一問一答」に出合い、やがて授戒を決意しました。

最近では、未来に希望を持てずに苦しんでいる学生が多いため、工導さんは、仏教の教えの一端を講義に盛り込み、少しでも生きやすい人生になるようアドバイスをしています。
中でもとりわけ大切にしているのが「人との関わりからの学び」です。なぜならば、ロボット工学は「人を知ること」から始まるといっても過言ではないからです。人と調和し協力できるロボットを産み出すためには、人の動き・考え・思いを綿密にくみ取り、それを的確に再現しなければなりません。

一方で、工導さんはこうも話します。「どこまで研究しても、ロボットは人間にはなれない」と。
だからこそ『人間の真理』である仏教を深く学び、より人間に近いロボットを産み出すべく研鑽を積むーー
「ロボットと仏教」一見すると遠いような2つの存在は、「人」を介して密接に結びついており、ロボット工学も、仏教徒のあり方も、人へのリスペクトが欠かせない世界です。冷静な研究心と、人への熱く深い想いをもつ工導さんは、実生活に仏教の教えをしっかり落とし込み、日々「教えの種」をまき続けています。
困難な時こそチャンス | 香月慈掌(こうげつじしょう)さん
つづいては、2020年に授戒した香月慈掌(こうげつじしょう)さん。生まれつきの重度脳性麻痺の息子さんを育てながら、障がい者のより良い環境を作ることを目指して、東京都北区で(株)ハビリ王子を経営しています。
息子の和平さんは現在28歳。医療面・療育(体の機能訓練)面、また親亡き後の未来の不安を解消したいとの想いから40代で医療資格を取得し、2022年となった今年、居宅介護事業所 Mama’sホームヘルプステーションを開設しました。

2年前に戒名を授かった瞬間、慈掌さんの目には涙があふれました。自分でも驚きましたが、心から安心しスッキリしたのを覚えているといいます。
そして、「これからをどう生きるか」という客観的な視点を得ました。今までつらいこともありましたが、「困難な時こそ行動のチャンス」であると気づき、「形にしなければ始まらない」と強く感じて会社設立に一層意欲を燃やしました。

慈掌さんは、大愚和尚が説く「型知(かたち)」の言葉に影響を受けました。これは、型にはすべて先人達の智慧(体験や経験によって得られる「気づき」)があるということを意味します。例えば、礼拝の方法である「五体投地(ごたいとうち)」はただの儀式の形ではなく、運動学として分析しても体に良い動きであると考え、今も毎日実践しているそう。
また、すぐに感情に流される自分の心を振り返り、「心はおろかである」と諦めて「幼な子のような自分を『そうかそうか』といさめては、前に進みます」と柔らかにほほえみます。

「息子がいるから、出会った人がいる。大愚和尚もそのお一人です」
困難は決してマイナスではない、むしろ行動するチャンスであるーー慈掌さんは、「どの人もその人らしく豊かに生きられるように」と、慈悲心を掌中の珠玉にして、今日も奔走しています。
●慈掌さんの経営する ㈱ハビリ王子 Mama’sホームヘルプステーションのホームページはこちら。
「生まれ変わればよいのです」|大愚和尚法話
ここからは、授戒会での大愚和尚の法話をご紹介いたします。

本日の授戒会は、よく事情がわからないまま参加されている方もいらっしゃると思います。まずは、授戒会がどのような儀式で、皆さんの今後の人生において、どのような意味があるのかをお伝えします。
そもそも授戒というのは、皆さんに「戒律」を授けるということです。律とは社会のルール、法律のことです。具体的に言うと複数の人が集まった際に、滞りなく物事を進めるためのもの。それを破った時には罰則があります。
では「戒」とは何か。「戒」とは、私たち個人のルールです。怠けてしまったり、調子にのってしまったりする自分のために設けるものです。しかし、あくまで個人的なものなので、破った時に罰則があるわけではありません。
いま皆さんには、十重禁戒(じゅうじゅうきんかい)という、10個の非常に重い戒が授けられました。しかしキリスト教のように神と契約したわけではありませんから、例え守らなくても、神様から何か罰を強いられることはありません。
「守らなければ、自分にマイナスの影響が起きやすい」という、ブッダが数ある道徳の中からセレクトした、皆さんを生きやすくするものです。
【十重禁戒】
1)不殺生戒(ふせっしょうかい)ーいたずらに命をあやめない
2)不偸盗戒(ふちゅうとうかい)ー自分に与えられていないものを奪わない
3)不邪淫戒(ふじゃいんかい)ー愛する人とだけ誠の愛を育む
4)不妄語戒(ふもうごかい)ー悪口や嘘をいわない
5)不酤酒戒(ふこしゅかい)ー理性をにぶらせる飲酒やギャンブルをしない
6)不説過戒(ふせっかかい)ー人の過ちを攻め続けない
7) 不自讃毀他戒(ふじさんきたかい)ー自らを褒め称えて、他をけなすようなことをしない
8)不慳法財戒(ふけんほうざいかい)ー自分の知識や財に執着し、出し惜しみしない
9)不瞋恚戒(ふしんにかい)ーかたくなになって怒り憎しみを増大させない
10)不謗三宝戒(ふぼうさんぼうかい)ー仏・法・僧の三宝をむやみに疑ったり、馬鹿にしたりしない

「そんなことは知っている」ということがほとんどかもしれません。しかし人は、たとえ飲酒運転はだめとわかっていてもしてしまう生き物なのです。だから改めて「人生のシートベルト」締め直す。それが授戒会です。
そして、最後にもう一つだけお話させていただきます。皆さんには、縁があって、命の種をこの世に産み出してくれた親がいます。なかには親に虐待をされた人もいるでしょう。自分の親が許せない。自分を生涯ずっと苦しめる存在。憎い、悔しい、でもどうしたらよいのか。そんな悩みを抱えている方もいることでしょう。
私は、それでもこう言います。「感謝をしてください」と。
嘘でもいいから、まずは「ご縁をいただきありがとう」と感謝をするのです。ブッダは「恨みをもって、恨みが消えることはない」と説きます。自分の人生といいながら、いつまでも親に縛られ続けていることに気づくべきです。
「心の炎症」を早く捨ててください。そして、生まれ変わればよいのです。戒を授かり、皆さんは今日「心のふるさと」を得たのですから。
編集後記
今回「仏教を学ぶ中で、なぜ新たに名前を授かるのか?」この問いに対する明確な答えを持たぬまま取材に向かいました。
しかし授戒後、愛おしそうに、そして力強く決心したかのように、自らの戒名を見入る参加者の姿を目の当たりにして、その意味を自然と理解することができたように思います。
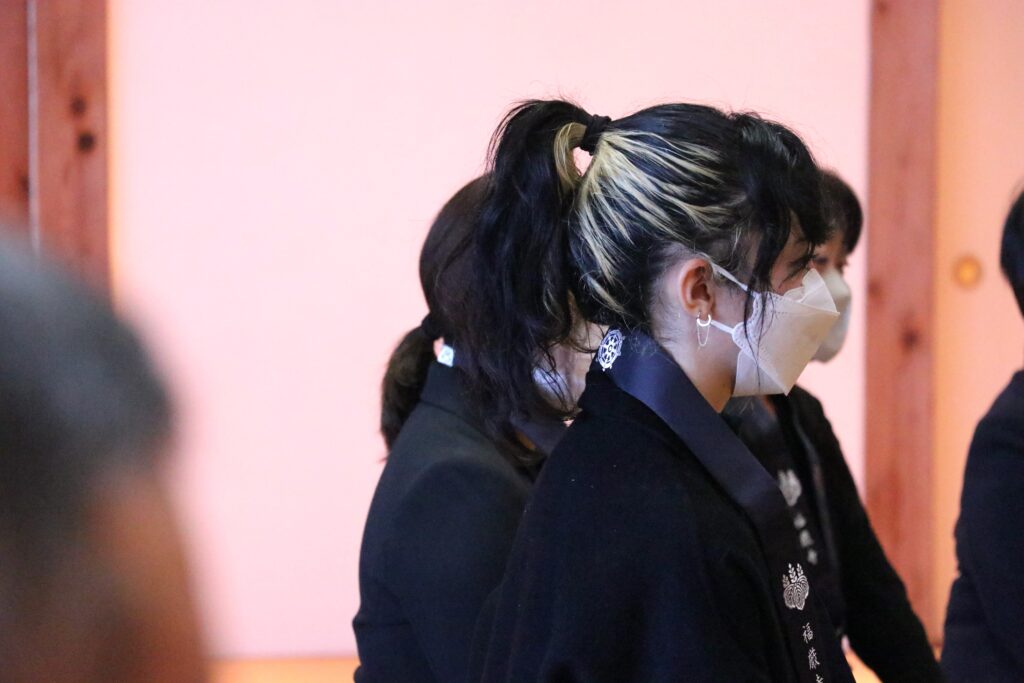
名前は、私たちが想像する以上に自分の環境を形づくり、導く力があります。それどころか先輩のお2人は、戒名の先に立ち、戒名の意味するところを牽引するような力強ささえ手にしているように感じました。
自分で自分を縛り続けるのではなく、「心のふるさと」を得て、また自由に新たに人生を始める。これもまた「人が幸せに生きる術」の一つなのかもしれません。
桐嶋つづる










コメント