2025年4月20日(日)、有明セントラルタワーホール&カンファレンスにて、「東京 経営マンダラ実践会」が開催されました。
会場は、東京臨海副都心に位置する利便性の高い複合施設。レストランを改変した空間は、赤と黒を基調とした高級リゾートを思わせる雰囲気です。
「経営マンダラ実践会」は2023年8月のスタート以来、回を重ねるたびに内容が充実。今年度からは時間を拡大し、内容もさらに切り込んだものとなっています。ここではそんな実践会の模様をご紹介します。
混沌としたこの時代、リーダーは何をするべきか
「経営マンダラ」は、世界一長寿な仏教教団と、世界一長寿な日本伝統企業に共通する9つの要素を、大愚和尚が独自の視点でマンダラ形式にまとめたもの。この内容を経営者やリーダーに向け伝えていくため定期的に開催しているのが、「経営マンダラ実践会」です。
この日、会場に集まったのは、経営者のほか、医師、政治関係者、教育事業関係者、ビジネススクール講師、これから起業を考えている学生、主婦など、職種も年齢も多種多様。みなさん静かに始まりのときを待ちながらも、その横顔からは並々ならぬ意欲が感じられました。
今回は、経営マンダラの9つの要素の一つ「広宣(こうせん)」をテーマに、2部制にて構成。広宣とは、いわゆるマーケティングのことで、自分たちを知ってもらうためにはどのような努力をすべきか、その工夫や方法と、その中に含まれた仏教のエッセンスについて学んでいきます。
冒頭、大愚和尚による開会のご挨拶がありました。
「この混沌とした時代に、経営者やリーダーのみなさんが、何を感じ、何に不安を抱き、これからどう生き、どう社会に価値を届けていこうとしているのか。そして、自らの道をどれだけ確信をもって歩んでいるのか。そのことをもっと知りたい」と、「経営マンダラ」にかける思いを語りました。

経営は「ありよう」 x 「やりよう」で決まる
第1部に登壇したのは、佛心宗の広宣(こうせん)チームのリーダー空拳(くうけん)さん。現在、整体事業の経営、佛心宗の僧侶、慈光グループ(大愚和尚が関わる仏教理念をもとにした事業グループ)の広宣に取り組まれています。
第1部では、「事業に掛け算をもたらす『広宣』の秘訣」をテーマに、さまざまな事例を紹介しながら講義が展開していきます。大愚和尚との出会いに始まり、ある事業がスタートし、店舗に行列を生み出すに至るまでの道すじ、そこから応用可能なポイントまでと、内容はかなり具体的に踏み込んでいて、それらはすべて自身の体験に基づいているだけに、説得力があります。
空拳さんは語ります。「広宣において最も重要なのは“誰”。“誰”に価値が提供できるのか?“誰”を喜ばせることができるのか?“誰”に求めらているのか?そこを明確にすることができれば、自ずとやるべきことは決まります」。そして、その後は仮説と検証の繰り返しであり、そのプロセスは「10回に1回(もしくは100回に1回)当たればいい方」という考え方がベースにあると説きます。
だからこそ、大切なのは「やり切る力」であり、そのために重要なのは心身の健康。心身を整えることも「ありよう」につながると話します。「“やりよう”は“ありよう”から生まれます。その人自身のありように問題があれば、どれだけやり方を学んでも、結果にはつながらないのです」。
最後に、自分ができることを「自分のためではなく、傍(はた:周り)を楽にする」ために行う。それには、お客さんはもちろん、家族や社員、周囲の人々の声に真摯に耳を傾けることが重要であると、2時間半に及ぶ講義を締めくくりました。

「ありよう」が変わると周りも変わる
今年度から時間を拡大してお届けする経営マンダラ実践会。ランチ休憩をはさんでの第2部は、今回からの新企画、参加者による自社プレゼンで幕が開けました。
このプレゼン企画は、参加者からの希望が反映されたもので、参加者同士が交流することで、新たなビジネスが生まれたり、経営者やリーダー同士の繋がりができれば、との目的から始まったものです。
初回となる今回は、プレゼンターの方の、社内の人間関係で悩みを抱えていた過去のお話や、そこから大愚和尚のアドバイスによってどのように変化、改善していったかについての、ご自身のお話が語られました。
大愚和尚が説く「永続する経営に欠かせない9大要素」を学び、実践することで、徐々に自身のありようが変わっていき、その結果、提供する商品や経営理念など、何ひとつ変えていないにも関わらず、社内の雰囲気や彼のもとに集まる人間関係、ひいては商品の売れゆきまでが変わっていったのだといいます。
リーダーの 「ありよう」が変われば、周り(利益、社員、家族、お客さん)が変わる。経営マンダラを学ぶことによってもたらされたリーダーの人格の成長が、良い結果につながったリアルなお話に、参加者のみなさんは共感と関心を持って聴き入っていました。

気づくこと、気づかせてあげること。人を育てて仏法の種を蒔く
自社プレゼンの時間が終わると、いよいよ大愚和尚の講義の始まりです。
「イノベーションと人材育成こそ仏教の歴史そのもの」。大愚和尚はそう説きます。
人を育てるうえで最も大切なのは「土壌づくり」であり、理念を根気強く伝え続け、その人の得意を見出し、その後はその人が「自分の感性を最大限に発揮できる」環境を与える。そうすることで、人は自ら気づき、成長していくのだといいます。
大愚和尚のもとに集う人々に共通しているのは、お金のために働いているのではないという点です。好きだからこそ、その道を選んでいて、仕事を「自分事」として捉えている。それゆえ、心が動いた瞬間に自然と行動に移していけるのです。
そんな「ありよう」を、6つの視点から紐解き、具体的な実践ワークとともに深めていくのが「第2部」の核心です。
福厳寺のご本尊である「観音菩薩」は、三十三のお姿に変化し、人々を導いていく慈悲の象徴としての仏様です。大愚和尚が手がける33の事業もその精神に根ざしたもの。「人々の苦しみに寄り添い、喜びを与える」ために、文字通り三十三観音のありようを実践していると語ります。
大愚和尚が示す6つの「ありよう」はどれをとっても、誰もが容易に理解できるもの。しかし実践するのは難しい。自身の「いまのありよう」に対する気づきがなければ実現しないからです。(具体的な内容はここでは書きませんので、ぜひ実際に参加してお確かめください。)
「ありよう」とはなにか。
「ありよう」とは、意識と身体の状態です。
お釈迦さまは、すべての苦しみは「無明」から生じると説きました。つまり、「知らないこと」「気づいていないこと」が自分の心を曇らせるのです。
しかし同時に、ほんの小さな気づきを得ることができれば、自分の心や環境に光をもたらすことができます。
これは、「さとり」のような大きなものではなく、たとえば、いまの自分の呼吸や手中にある物の重さに気づくというような、些細なことです。
その些細な気づきこそが、人生を少しずつ、しかし確実に変えていくのです。
大愚和尚が手がける「ありよう」の実践ワークは、その「小さな気づき」をベースに展開していきます。
「世界が重い」と感じるとき、実は重いのはこれまで当たり前になっていた「自分という枠」かもしれません。他人の視線、過去の記憶、期待と役割、そのすべてに無自覚なまま、私たちは動かされ、疲れ果てていきます。
けれども、ほんの一瞬、意識の置き方を変えるだけで、身体の重心が変わり、言葉の響きも、人との距離も変わっていく。自身の「ありよう」を変えることは、 「どのように生きるか」を選び直すことであり、それによって、この世界のありようも根本から書き換わっていきます。
この日、そのことを実践ワークを通し学んだみなさん。経営者に求められる「ありよう」とは、一体何だったのか…。そのことを問いかけるまでもなくその答えは、みなさんの晴れやかな表情から、読み取ることができました。

<編集後記>
今年度最初の経営マンダラ実践会。朝の会場には凛とした空気が漂っており、参加者のみなさんからは一様に意気込みが感じられました。そして、いざ講義が始まると、その場の空気は、どんどん熱を帯びていきます。真剣に学ぶみなさんの姿が、講義が進むにつれキラキラと光り輝いてくる。佛心の智慧とは、かように人々に勇気と喜びを与えてくれるものであるのだと確信することができました。
「智慧を共有し、蟻が集まって象になろう」。開会のご挨拶の際、大愚和尚がおっしゃっていたこの言葉が、まさに具現化したような、そんな貴重な一日でした。
取材:香薫理掌
「佛心経営マンダラ」について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
→ 経営マンダラホームページ https://mandala.busshin.or.jp


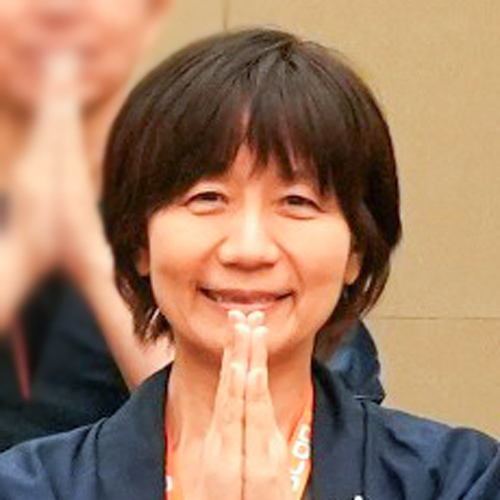
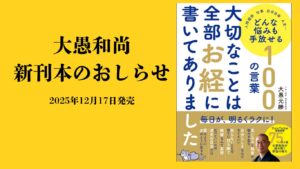




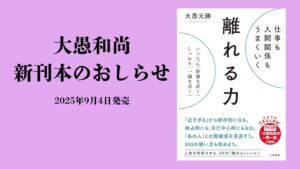
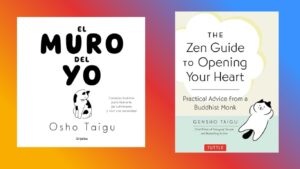
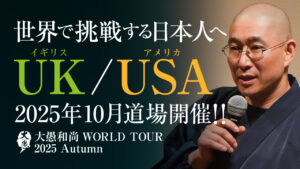
コメント