◆前記事のあらすじ
2024年12月7日(土)に行われた、福厳寺あきば大祭。お祭り広場が賑わう一方、秋葉本殿では1年に1度の加持祈祷(ご祈祷)が行われました。
そして夕闇が迫る頃、観音菩薩の「知恵の燈」を運ぶ松明(たいまつ)行列を皮切りに、特別法話や儀式の核心となる火渡りへと続きます。
聖俗を切り替える松明の炎

法螺貝の音とともに境内を巡る、いくつもの松明。だんだんと陽が傾くにつれ、その炎の揺らめきと明るさは、いっそう際だちます。
僧侶、修験者、天狗に扮した赤い衣服をまとった先導者。歴史や伝統を体現した、厳粛な行列が人々の間を歩みます。
日中の楽しい雰囲気のお祭りから、古式ゆかしい伝統の儀式へと、全体の雰囲気も入れ替わります。
そして観音菩薩からいただいた、「智慧の燈」である松明の火が、秋葉本殿に納められると、本堂では大愚和尚のお話が始まります。
【あきば大祭2024】大愚和尚・特別法話

「私たち人類は火の力で、豊かな文明を築いてきました。
しかし、その扱いを一歩まちがえれば、皆が火に焼かれてしまいます。
今は消防が発達しましたが、火事は毎年起きており、報道されているのはほんの一部です。依然として火事は大きな脅威なのです。
それでも早い段階で消防車が到着すれば、全焼をまぬがれることもあるでしょう。
しかし皆さんの、「心の中の火」はどうでしょうか。
日ごろ皆さんの周りでは、たくさんの怒りの声が聞こえてはいないですか?
あれが気にくわない、自分を大事にしてくれない、思ったようにならずイライラする。
とどまることを知らない、その欲や怒りの火は、だれが消してくれるのでしょうか。
他の誰でもない、自分の欲望や怒りは、自分で整えていくしかないのです。

仏教では、欲望や怒りや無知の心を「三毒」と捉え、その三毒を火に例え戒めています。
だからこそ福厳寺では毎年、大きな火を焚いて、皆さんにも渡っていただきます。
オール電化が進み、日常で火に触れることが少なくなった現代だからこそです。
火は熱い、火は危ない、そして心の中の三毒の火も同じです。
そのことを1人でも多くの方に、火渡りを通じて体感して頂きたいのです。
さて、私たち日本人は古来より、新しい命を生み出す自然を、大いなる神として崇めています。
しかし、日本にはそれとは別の神の姿がありました。
それは私たちと同じ人間でありながら、人間業とは思えないほどの功績を遺した人物が、死後に神格化された存在です。
その1人が、火難から人々を救う誓願を立て、全国を行脚し火を収める技術と知恵を広めた、秋葉三尺坊大権現です。
物理的な火とともに、心に潜む三毒の炎を三徳に変えよと、その教えを私はくり返し皆さんにお伝えしています。

三徳とは何か。
1つ目は「恩徳(おんとく)」です。
私たちは1人で生きているわけではありません。家族や地域の人々、社会も自然も、多くの方や環境によって生かされている。そういう存在のおかげで生きているという、当たり前のことを忘れてはいけません。
そのような感謝の心を自覚すれば、「今だけ、金だけ、自分だけ」という、ワガママな態度にはなり得ません。
2つ目は「断徳(だんとく)」です。
これは「自分の欲や怒りを断ち切る」ということです。
どうしても悔しいことはある、腹が立つこともある。しかしこれを感情のおもむくままに、際限なく怒り続けたら、どうなりますか。きっと怒りの火に焼き尽くされてしまうことでしょう。そう思うと、どこかでぐっとこらえて、断ち切らなければならないのです。
そして、3つ目は「智徳(ちとく)」です。
私たちはよく知らないのに、知ったふりをしたり、噂話のような情報に踊らされたり、愚かな行いをくり返してしまいます。
だからこそ「正しい知恵」が必要です。
『火事は怖いですよね、わかります』。これは本当にそうでしょうか。
知識で想像するのと、身をもって実際に体験するのでは、感覚がまったく異なります。
だからこそ、このあきば大祭では命を脅かすほどの、実際の火を渡り『火は熱い。火を馬鹿にしてはいけない』という事実を、肌身を通して体感して頂きます。
あきば大祭の炎は、決してエンターテイメントではありません。
この火の中で立ち止まれば、本当に焼けこげてしまいます。
だからこそ、その気づきと覚悟をもって、火を渡る際は、真剣に確実に、歩みを進めて欲しいのです」。
自灯明の覚悟で歩む道

ひとつずつは小さく、温かみさえ感じた松明の炎。
しかし、それらが斎場へと降ろされた途端、みるみる燃え広がり、人間の背丈を超し、建物の二階三階に迫るほどの、燃え盛る火柱と化していきました。
その炎から生じる熱風は結界の旗を揺らし、前列の参拝者の中には、思わず顔を背ける方もいました。
僧侶たちは、燃え盛る火の結界を時計回りにゆっくりと歩み、秋葉真言(あきばしんごん)を、くり返し唱え続けます。
オンピラピラケンピラ、ケンノンソワカ
オンピラピラケンピラ、ケンノンソワカ


この火を最初に渡る大愚和尚は、炎の動きを観察し続けます。
そして適切なタイミングを見極めた瞬間、迷うことなく炎の道へ突き進みました。そのあとを間髪入れずに、他の僧侶たちも続いていきます。
さらに大愚和尚たちが切り開いた火の道を、一般の参拝者たちも次々に進んでいきました。
その間も秋葉真言や法螺貝の音、また僧侶の見守りが続きます。
待ち受けるのは火の熱さだけではありません、ときに視界をさえぎる煙も立ち込め、目鼻が痛む場合もあります。
それでも身ひとつで歩むのが火渡りの儀であり、誰かに代わってもらったり、お金を払えば防火服が貸されるといった、特別扱いはありません。
どのような人間であれ、この結界の中では一切のウソやごまかしが通用せず、自分の心と身体を拠り所として、火の道を進むほかありません。
そのような中、前方をまっすぐに見据え、合掌したまま歩む方。
少しよろめきながらも、懸命に進む方。前を歩む方の姿は、後ろに待機する方にどれほどの勇気を与えていることか、はかり知れません。一つのことに集中して懸命に歩む人の姿は、それを見るすべての方の、心を揺さぶる力を持っています。

大人も子供も年配の方も、火の道の中では、一人ぼっちです。
ふと怖さを感じたのか、一人の子供が熱さと恐怖で、立ち止まって泣き叫ぶ瞬間がありました。しかし火の道の途中で立ち止まったり、引き返したりする行為は、たいへん危険です。
その状況を察知した僧侶が、間髪入れずに子供に歩み寄り、出口までその子を抱きかかえて事なきを得ました。
その子は、とても怖い思いをしたに違いありませんが、人生において忘れられない経験として、テーマパークやエンターテイメントの場では、決して得られない学びがあったことと思います。
当日は1000名を超える参拝者が火を渡りましたが、すべての方に危険が及ばないよう、結界内の僧侶は片時も集中力を切らしません。
また結界の外側においても、地元の消防団や奉賛者が、万一の事態に即応できるよう備えています。
このように、参拝者を見守る多くの人々によって、この儀式が成り立っている事実が、肌身に感じられました。
あきば大祭に抱いた想い
ここまで取材班の目線を中心にお伝えして来ましたが、実際に参加された方は、どのような想いを抱かれたのでしょうか。
火渡りの前後にお話を伺えた方がいらっしゃいましたので、その一部をご紹介したいと思います。
【インタビュー①】坂本さん(東京都)

今日は福厳寺へ初めて、1人で足を運びました。知り合い等はいなかったのですが、皆さん親身で話しやすく、とても楽しめています。
私は1年ほど前、さまざまな悪いことが重なり、人生に大きな落ち込みを感じていました。
そのようなとき、YouTubeで「大愚和尚の一問一答」に出会い、光明を見出しました。
そして大愚和尚のお話を、ぜひ直接お聞きしたい、そして御祈祷を受けたいと思い、本日やって参りました。
火渡りの際、私は先頭から3列目に並んでいましたが、それでも最初の火が燃え上がったとき、吹きつける高熱の空気には、思わず合掌した手を放して顔を覆ってしまいました。
「こんなにも熱いのか」という驚きとともに、「あれは自分の、心の三毒なのだ」と肝に銘じて臨みました。
そして渡り終えた瞬間は何とも清々しく、本当に心が浄化されたような気がしています。ありがとうございました。
【インタビュー②】青山さん(大阪府)

私は大阪でマスターズ陸上100m走で、選手として活動しています。一方で短距離走を教えるコーチとして、クラブチームで50人ほどの子ども達を指導しています。
そうしたなか、現代の子どもを取り巻く環境について、良くも悪くも守られ過ぎていると感じる瞬間があります。
最近では仏教で言う『忍辱(にんにく:やりたくないこと、逃げたいことと正面から向き合い、むしろその気持ちを、楽しみに変えて取組む姿勢 )』の心構えを、うまく伝えられたらと考えています。
このあきば大祭でコーチングのヒントを、何かしら得られたらという思いもあり、参加しました。
火渡りにはクラブチームの白いユニフォームで臨みましたが、色々な人から「焦げちゃうかも知れないよ」と心配していただきました。
でも焦げたら焦げたで、それも良い思い出かなと。
しかし、いざ火の道に足を踏み入れると、その熱さには本当に驚きました。
そして、これが心の炎だとすれば、その恐ろしさも思い知らされたように感じます。
それでも火渡りを達成し、そこで得られた気付きに対して、やってみて本当に良かったと思えています。
この事はまさに自分の体験として、子どもたちに伝えることが出来ます。
今日の学びを、ぜひ今後の指導に取り入れて行きたいです。
編集後記

この記事では冒頭に「これほど多くの方が、あきば大祭に集うのか何故か?」という書き出しで、始めさせていただきました。
それは佛心宗の発信するメッセージが、SNSやさまざまなインターネットの口コミを通じて、多くの方に届いている側面が、大きいように感じます。
しかし全体の取材を通じ、それだけではないという実感を得ました。
効率や安全を重視しすぎた、現代の生活において、人間の動物的本能が「火の熱さ、恐ろしさ」を体感することを求めているような、生き物として大事なことを忘れてはいけないという、身体からのメッセージのようにも感じます。
私たちが、あえて不便な自然の中でキャンプをすることも、そのような本能的な部分が関係しているように思います。

「祭り」が持つ3つの力、「人が集まり、その中でリーダーが生まれ、共同作業をする中で、人々が結びついていく」。その光景を、このあきば大祭を通じて、実際に見て聞いて、体感することができました。
何時間もかけて、飛行機と電車とバスを乗り継ぎ、福厳寺を訪れる人々。
佛心誓願のもと自らを反省し、その大切さを心に刻むために、燃え盛る炎を一人突き進んでいく人々の姿を見るにつけ、日本人もまだまだ捨てたものではないと感じる瞬間がありました。
室町時代から続く伝統を守りつつ、新たな人々がこのお祭りを通じて結びつき、あきば大祭はこの先もますます大きくなっていくことでしょう。
そのような思いを強く抱いた1日となりました。
取材者:原田ゆきひろ,山田かよ
2025年のあきば大祭は12月6日(日)です。一年の心の汚れを取り除き、清らかな気持ちで新しい年を迎えるための、心の節目となる一日です。そして、その場で新たな善友とのご縁が生まれるかもしれません。詳細は、近日中に福厳寺の公式ページに掲載されます。皆さまのお越しをお待ちしております!
2025年福厳寺あきば大祭公式WEBはこちら
https://akiba.fukugonji.com/






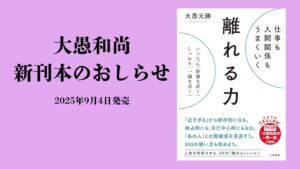
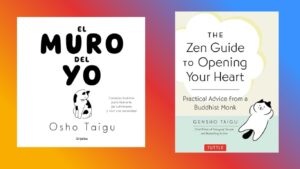
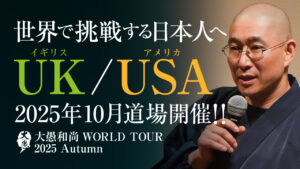


コメント